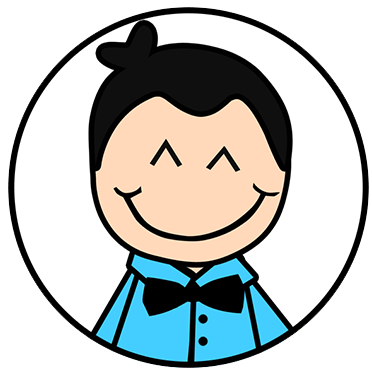経営メモ > 書店 amazon、コンビニによる雑誌販売、古本チェーン店により、昔ながらの書店はどんどん減っている。100円で買える電子書籍などは、もう書店で扱うことすらできない。 #業界のトレンド・特徴 #減少 |
- 経営全般
- マーケティング(58)
- 経営戦略(56)
- 全業種共通(46)
- 組織マネジメント(36)
- 開発マネジメント(31)
- 飲食業界共通(31)
- GAFA(22)
- ビジネスモデル(22)
- 経営全般(20)
- 営業ノウハウ(19)
- ネット
- オンラインショップ(46)
- SEO・SEM(22)
- WEB制作(7)
- ECコンサルタント(7)
- ネットオークション代行(4)
- 飲食店
- 喫茶店(16)
- 総菜店(14)
- 居酒屋(12)
- お弁当店(9)
- フランス料理(9)
- ラーメン店(8)
- ベーカリー(8)
- 移動販売(8)
- 無国籍料理(8)
- ワイン・バー(8)
- 郷土料理(8)
- 立ち飲み(8)
- 洋・和菓子(8)
- バー(7)
- 食材宅配サービス(7)
- 焼鳥店(7)
- 立ち食いそば(7)
- ドッグカフェ(6)
- 給食業(6)
- ファミレス(6)
- カレーショップ(5)
- お好み焼き店(5)
- 定食屋(5)
- 宅配ピザ店(5)
- スポーツバー(5)
- 中華料理店(4)
- スナック(4)
- アイスクリームショップ(4)
- おにぎり専門店(4)
- パスタ専門店(4)
- 高級和食店(4)
- うどん店(3)
- イタリア料理(3)
- 回転すし(3)
- 丼物専門店(3)
- ステーキハウス(2)
- 流通
- コンビニエンスストア(20)
- FCフランチャイズ(18)
- ミニスーパー(7)
- ゴルフショップ(6)
- ディスカウントストア(4)
- アウトレットモール(4)
- ホームセンター(3)
- ドラッグストア(3)
- ショップ
- セレクトショップ(15)
- 書店(12)
- 100円ショップ(11)
- 美容室(11)
- 金券ショップ(11)
- アクセサリーショップ(11)
- 靴販売店(9)
- 花屋(8)
- 1000円カット(7)
- 園芸店(7)
- 雑貨ショップ(7)
- CDショップ(7)
- 携帯ショップ(7)
- 貴金属買取ショップ(7)
- DPEショップ(6)
- 玩具店(6)
- ボックスショップ(6)
- インテリアショップ(6)
- アンティークショップ(6)
- 自然食料品店(6)
- 調剤薬局(5)
- プリントショップ(3)
- 理髪店(3)
- 化粧品販売(2)
- CD・DVDレンタル(2)
- 手芸用品店(2)
- サービス
- マッサージ・リラクゼーション(21)
- コイン駐車場(15)
- ネイルショップ(12)
- インターネットカフェ(11)
- ペットショップ(11)
- 家事代行(9)
- 保険ショップ(8)
- アロマセラピー(8)
- ペット葬祭業(8)
- ペットホテル(7)
- 歯科医院(7)
- 結婚相談所(7)
- エステティック(7)
- ハウスクリーニング(7)
- 学習塾(6)
- 弁当宅配サービス(6)
- ペットシッター(6)
- 引越サービス業(6)
- カラオケボックス(6)
- 家庭教師派遣(4)
- ゲームセンター(4)
- ペット美容院(4)
- 許認可外保育施設(3)
- ミネラルウォーター販売(3)
- 合い鍵業(3)
- クリーニング店(3)
- 鍼灸院(2)
- スクール
- ダンス教室(12)
- 語学学校(11)
- 囲碁・将棋クラブ(10)
- 料理学校(9)
- フィットネスクラブ(9)
- ビジネススクール(7)
- 資格学校(6)
- パソコンスクール(6)
- カルチャースクール(6)
- ダイビングスクール(4)
- 旅行
- 観光農園(10)
- ペンション(9)
- 民宿(8)
- 旅行会社(8)
- ビジネスホテル(7)
- 土地建物
- 建築設計事務所(13)
- アパート・マンション経営(8)
- ビルメンテナンス業(7)
- トランクルーム(5)
- スーパー銭湯(4)
- 警備保障業(2)
- 運送
- バス・タクシー・ハイヤー会社(10)
- 運送業(6)
- 自動車整備業(6)
- 運転代行業(4)
- ユーザー車検代行業(4)
- 介護
- 介護用品の販売・レンタル(9)
- 高齢者向賃貸住宅(7)
- ケアハウス(6)
- 介護士派遣業(5)
- 有料老人ホーム(4)
- 特別養護老人ホーム(3)
- デイサービス(3)
- リサイクル
- 古着屋(10)
- 中古家具販売店(7)
- 子供服のリサイクル(7)
- リサイクルショップ(7)
- 中古自動車販売(6)
- 靴修理サービス(5)
- 内装リフォーム業(5)
- 古本屋(5)
- 再生資源回収(4)
- レンタルオフィス(4)
- 中古パソコンショップ(3)
- レンタルブティック(3)
- 衣服リフォーム(2)
- 法人サービス
- 情報システム開発(9)
- 人材紹介業(9)
- 翻訳通訳業(9)
- デザイナー(7)
- 広告代理店(5)
- コピーライター(5)
- カメラマン(5)
- 不動産鑑定士(5)
- テクニカルライター(4)
- CGクリエーター(3)
- 人材派遣会社(3)
- 経営コンサルタント(3)
- キャリアカウンセラー(3)
- その他
- つぶやき(153)
- アフターコロナ(83)